最終更新日
公開日
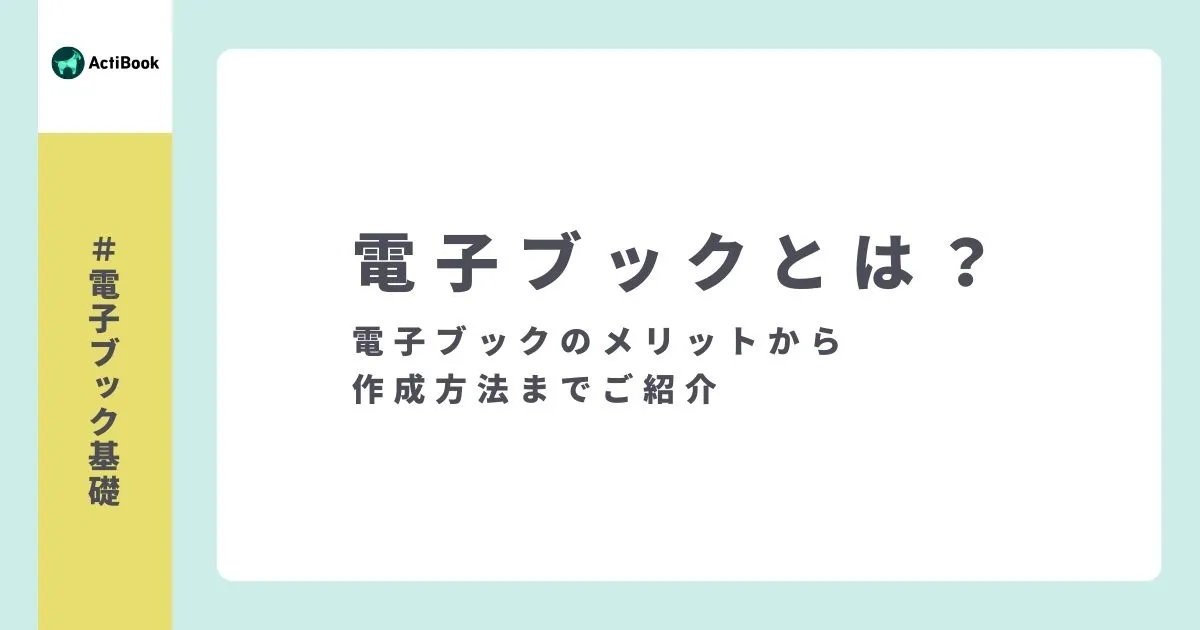
パソコン・タブレット・スマートフォンなど様々な媒体から気軽に利用できる電子ブックは、その利便性・訴求力の高さから、現在あらゆる業界において導入が進んでいます。
本記事ではメリットや作成方法、導入費用など、電子ブックについて詳しくご紹介します。
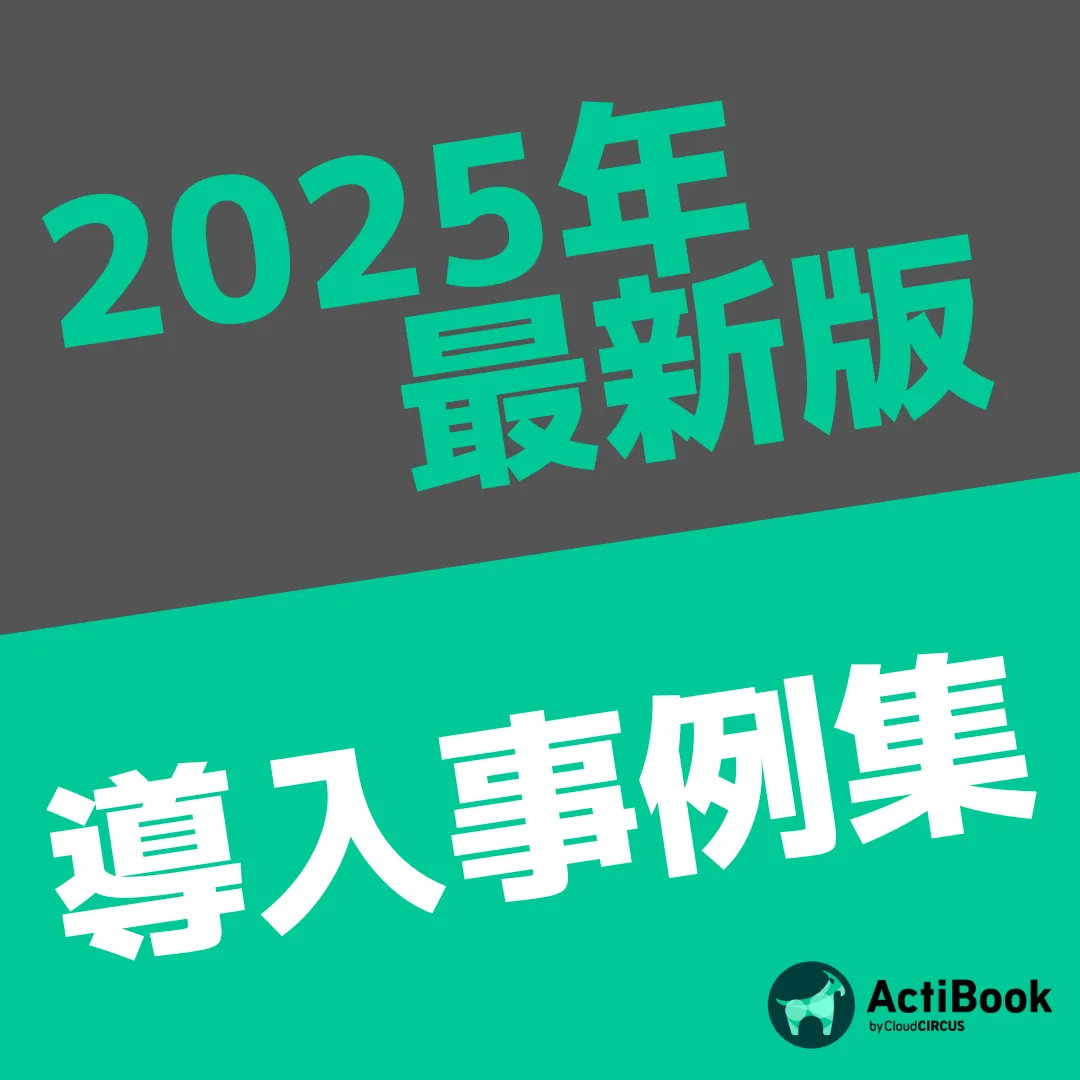
【2025年最新版】ActiBook導入事例集
ActiBookを導入いただいたお客様の事例をまとめております。導入前の課題から運用方法、具体的な成果まで図解とともに紹介しています。
資料ダウンロード(無料)目次
電子ブックは、PCやスマートフォンなど多様なデバイスで閲覧でき、紙のようにページをめくる操作性と、動画・音声の組み込みやログ取得といったデジタルならではの機能を両立させている点が特徴です。
一般的なPDFと比較した場合、以下のようなメリットがあります。
これらのメリットから、電子ブックは集客ツール、教育ツール、ユーザー向けツール(マニュアルなど)として幅広く活用できます。 作成方法については「電子ブック作成ツール」の利用と「制作代行」の2種類が紹介しており、弊社の無料で利用できるActiBook(アクティブック)を紹介しています。
電子ブックとは、一般的にWeb上で表示可能な電子冊子のことを指します。Web上でも実際の紙媒体を読んでいるような見せ方ができるのが特徴で、ページをめくるような使用感でコンテンツを閲覧することができます。
また、電子ブックでは、音声や動画などの掲載や、ログデータの取得、テキスト検索など、紙媒体では不可能なコンテンツ・機能を活用できるのも大きな魅力です。機能をうまく活用すれば、情報を伝えるだけでなく、効果的なマーケティング活動へとつなげることもできます。
電子ブックには、カタログやパンフレット、雑誌類など、ビジュアルが多く使用される「画像(FIX型)」と、電子小説や読み物として使われる「リフロー型」の2パターンあります。
「画像(FIX)型」は、カタログ・資料用として普及しており、既存の紙データを2次利用できるのが特徴です。専門知識がなくても数分で作成できるというメリットがあります。
一方「リフロー型」は電子書籍用として普及しており、端末に最適化することができます。このパターンを作成するのには専門知識が必要で、制作日数は2日以上かかることが多いです。
株式会社デジタルベリーが行った「デジタルカタログ市場調査アンケート 第4回」では、電子ブックは過半数(54.3%)のユーザーに便利と感じられていることがわかっています(不便と感じたのは16.6%)。
特に「紙でカタログを保管する必要がない」「紙媒体と近い感覚で操作できる」「資料請求が不要なため手間がかからない」など「保管不要・操作性・手間いらず」という点が支持されています。
電子ブックは主に集客ツール、教育ツール、ユーザー向けツールの3つの目的で活用されています。
商品カタログ、パンフレット、高校や大学案内、スーパーのチラシなどを電子ブックに変更します。
電子ブックに変えることで、顧客は資料ダウンロードや資料請求を行う手間をかけずに、気軽に情報にふれられるようになります。メルマガに電子ブックのリンクを記載して多くの人に情報を届けたり、動画を資料に組み込んで視覚的にアピールしたりも可能です。パンフレットやカタログの機能を拡張して、商品の魅力を様々な角度からアピールできるようになるでしょう。
製品マニュアルや従業員向けのトレーニングにも電子ブックが活用されています。
例えば、新人社員向けのトレーニングマニュアルを電子ブックに変えて、各セクションに動画やインタラクティブなクイズなどを配置します。楽しみながら学べるトレーニングを提供できれば、学習者の興味関心を刺激して、スキル向上や業務理解を早めることができるでしょう。動画やインタラクティブな仕掛けを組み込むことで、学習効果の向上・理解向上を手助けする効果的な学習環境を構築できます。
また、電子ブックは閲覧環境があればどこにいても閲覧できます。業務の進め方で悩んだときに素早くアクセスできるため、資料を探したり、悩んだりする時間を短縮できます。
製品やサービスの利用方法をユーザーにわかりやすく伝えたい場合は、電子ブックが役立ちます。
操作マニュアルやヘルプページを電子ブックに変換することで、ユーザーは必要な情報に簡単にアクセスでき、問題解決やトラブルシューティングをスムーズに行えるようになります。検索機能を組み込めば、ユーザーエクスペリエンスの向上も期待できます。文章の補足で動画を入れるとさらにわかりやすく、詳しい情報が伝えられるでしょう。
電子ブックへの疑問としてよく挙がるのが「PDFとの違い」です。本章では電子ブックとPDFとの相違点を詳しくご説明します。
電子ブックでは音声や動画を埋め込むことができるため、リッチコンテンツとして活用することが可能です。PDFにはURLを貼り付けることはできますが、埋め込みはできません。
また、電子ブックでは画像の切り取りやメモ・ペイントの書き込みが可能で、それらをシェアすることもできます。
PDFは縦スクロールで読みますが、電子ブックは本やカタログをのような感覚で、ページをめくりながら読めます。
PDFの縦スクロールだと、資料数が多い場合は読み飛ばしたり、読みたいページがどこか分からなくなったりと、扱いにくさを感じることがあります。しかし電子ブックなら、読み飛ばさず、目的のページにすぐたどり着けます。
電子ブックの表示速度はページ数の多さに左右されません。Webコンテンツとして表示するため、Webページを読むような快適さで閲覧できます。また、好きな箇所から読み進められるのも特徴です。
一方、PDFの場合は、全てのデータを1度ダウンロードしてから表示します。データが多いと表示するまでに時間がかかり、「重い」と感じることもあるでしょう。一部だけ閲覧したい場合も、全データのダウンロードが必要です。
動画や音声の埋め込みはPDF、電子ブックどちらでも行えます。しかし、PDFの場合は埋め込み用のツールが必要です。また、埋め込めば埋め込むほど表示速度が遅くなります。
電子ブックはツールを使わずに埋め込めて、表示速度もスムーズです。文章、画像、動画、音声を組み合わせた、よりユーザーに伝わりやすいコンテンツが提供できます。営業資料や学校案内のパンフレットにPR動画を取り入れたり、商品説明に操作方法の動画を掲載したりと、様々な活用方法が考えられます。
PDFでは、一度ダウンロードされたものを最新の情報に更新したり、記載されているデータを削除したりするなどの管理ができません。電子ブックでは、情報を差し替えるだけで、閲覧者側の電子ブックデータを全て最新のデータに変換することができるため、常に最新の情報をユーザーへ提供することができます。
資料を配信した際に、PDFでは「○人が資料をダウンロードした」ということしかわかりませんが、電子ブックでは「どのページがどれくらい見られたか」というより詳細なログデータを取得することができます。取得したデータを解析することで、恒常的に業務を改善していくことが可能になります。
同じ媒体を電子ブックとPDFで見せたときに、どのような読まれ方の違いがあるのかを調査した実験において、「電子ブックはPDFに比べて全頁確認されやすく、最後まで読まれやすい」という結果が出ています。またgooリサーチの調査では、PDFはユーザーから嫌われる傾向にあることが判明しており、電子ブックとPDFのには「読まれやすさ」という点において、大きな違いがあるといえるでしょう。では電子ブックにはどのようなメリットがあるのでしょうか?次章で詳しくご紹介します。
電子ブックの導入には従来の印刷物では叶わなかった、デジタルならではの様々なメリットがあります。
電子ブックは紙を使用しないため、従来掛かっていた印刷代や製本代などのコストを大幅に削減できるというメリットがあります。郵送も不要となるため、郵送代や郵送に係る工数を削減することも可能です。
企業によっては電子ブックを導入することで数百万円のコスト削減を実現しています。
電子ブックは知識不要で誰でも簡単に作成できるのが大きな魅力のひとつです。作成した電子ブックはユーザーにURLを共有するか、Webサイトに埋め込むだけで即座に公開できます。
また、印刷物では印刷後に修正が必要となった場合に刷り直しや資料の再送など大きな労力を要しますが、電子ブックでは、公開後でも新しい資料に差し替えるだけで共有したURLはそのままで、ユーザーに正しい情報を届けられます。
例えば、カタログの商品名に誤字が発覚した場合、元データを修正して電子ブック作成画面に修正データを再アップすると、公開済の電子ブックが自動で修正後のデータに更新されます。また、社内マニュアルを最新のものに差し替える際にも、電子ブックであればURL再共有が不要になるので便利です。
紙を使用しないため部数の制約がなく、より多くのユーザーに資料を閲覧してもらえます。一度公開してしまえば、閲覧数に制限がなく公開を維持できることに加え、在庫切れや増刷のための追加費用の心配も不要。
少ないコストでより多くのユーザーにアクセスしてもらうことが可能になります。
電子ブックでは、ダウンロード数だけでなく、資料の閲覧数やどのページが多く読まれたかなど詳細なログデータを計測することができます。
取得したデータを分析してマーケティング戦略に活かすなど、資料公開後の恒常的な改善に利用でき、コンテンツの品質向上へつなげられます。
電子ファイルによる情報提供では、ユーザーが利用するデバイスによって表示できなかったり、フォントやレイアウトが崩れてしまったりするという問題があります。電子ブックはどのデバイスでもブラウザからアクセスできるので、ユーザーの環境に依存せずにコンテンツを提供することができます。また、デバイスひとつで場所を選ばずに閲覧することができるため、営業活動における利便性の良さもメリットのひとつといえるでしょう。
電子ブックのメリットについて詳しく見てきましたが、実際に作成するためにはどのような方法があるのでしょうか?
電子ブックの作成方法は2つあります。1つは「電子ブック作成ツール」、もう1つは「制作代行」です。では、詳しくみていきましょう。
電子ブック作成ツールにはPCにインストールして利用する「PCソフトウェア型」と、ブラウザベースで制作作業が完結する「SaaS/クラウド型」がありますが、本記事では誰でも簡単に利用できる「SaaS/クラウド型」をご紹介します。
「SaaS/クラウド型」作成ツールの最大の特徴は、ブラウザ上で利用できるため、インターネット環境があればいつでも誰でも電子ブックを作成できるという点です。シンプルな機能で制作難易度も低く、難しい知識がなくてもすぐに作成することができます。
また、作成ツールでは自分でコンテンツを管理できるため、好きなタイミングで資料の更新ができるなど、自由度が高いというメリットがあります。無料で利用できるツールも登場しているので、「まずは試しに電子ブックを利用してみたい」という方にもおすすめの作成方法です。
制作代行は、印刷物の原本を業者に渡して、スキャンから電子ブック化までを代行してくれるサービスです。「1冊○○円〜」と費用がかかるほか、冊数やページ数によって従量課金が発生するため、1回のみの制作で済むユーザーや、更新頻度が低いユーザー、予算が豊富にあるユーザーなどに向いています。コンテンツの更新や修正では、内容を逐一指示する必要があるため、作成ツールに比べると自由度は下がるでしょう。
電子ブックについてよくわかったところで、「試しにどんなものか利用してみたい」と思われた方もいるのではないでしょうか。そこでおすすめしたいのが、無料で体験できる電子ブック作成ツール「ActiBook(アクティブック)」です。
「ActiBook(アクティブック)」は、誰でも簡単にわずか3ステップで電子ブックを作成できます。
フリープランでは3ファイル(上限50MBまで)までアップロードすることができます。
電子ブック本棚サイト機能や分析機能など、便利な機能もフリープランで利用することが可能です。導入・公開を簡単に行える機能が充実し、パソコンの操作が苦手な方でも扱いやすいサービスとなっております。
20,000社(2024年5月末時点)が導入している「ActiBook」。電子ブックの導入を検討している方は、まずは試しに利用してみることをおすすめします。



ActiBookは顧客の興味行動が分かり 効率的・効果的なセールス活動を 促進する電子ブック作成ツールです
ダウンロード資料の内容