最終更新日
公開日
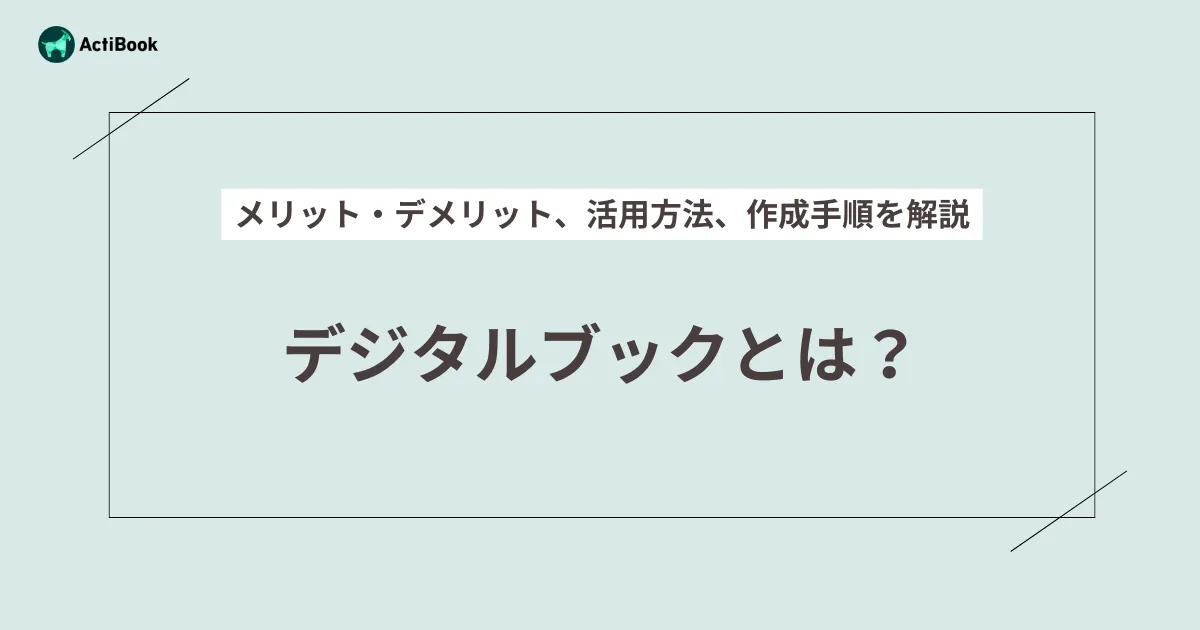
デジタルブックについて、「PDFとの違いは?」「導入するメリットはあるのか?」「どのような方法で作成できるのだろうか?」といった疑問をお持ちの方もいるでしょう。
パソコンやスマートフォンなど、多様なデバイスから利用できるデジタルブックは、紙のような操作性を持ちながら、ログ取得や動画埋め込みといったデジタルならではの強力な機能を持っています。
この記事では、デジタルブックの定義や、PDFとの違いから、具体的な活用目的(集客・教育など)、そして「作成ツール」と「制作代行」の2種類の方法まで、導入検討に必要な情報を解説します。この記事を読むことで、デジタルブックの全容と、自社に最適な導入方法を理解できるでしょう。
目次

デジタルブックとは、紙の書籍やカタログのようにページをめくる感覚をデジタル上で再現したコンテンツです。PC、スマートフォン、タブレットなど、Webブラウザから手軽に閲覧できる電子冊子のことを指します。電子ブックやe-bookとも呼ばれます。
デジタルブックの最大の強みは、テキストや画像だけでなく、リンク、動画、音声といった多様なメディアを組み合わせて構成できる点です。これにより、静的な紙媒体では提供できなかったリッチな情報と快適な閲覧体験を読者に提供します。
単にデータを持ち運びに便利なデジタル形式にしただけでなく、文字サイズの調整、キーワード検索、そして誰が、いつ、どこを見たかというログデータ(アクセス解析)の取得など、紙媒体では不可能な高度な機能を利用できるのが特徴です。
その用途は幅広く、顧客向けのカタログやパンフレット、製品マニュアルといった販売促進・ユーザーサポートだけでなく、社内向けのマニュアルやトレーニング資料にも活用され、業務効率化や環境負荷の低減(ペーパーレス化)にも貢献するツールです。
デジタルブック作成ツールの多くは、基本的な機能として、テンプレートの利用、画像やテキストの挿入、ページの追加・削除が可能です。さらに、動画やECサイトへのリンクを組み込むことで、顧客の興味を引きつけるインタラクティブなユーザー体験を提供し、直接的なコミュニケーションを促進できます。
参考:デジタルブックを無料で作成する方法とは?おすすめツールと活用法を紹介
デジタルブックは、コンテンツの形式や用途によって、主に以下の2つのパターンに分けられます。
株式会社デジタルベリーが行った「デジタルカタログ市場調査アンケート 第4回」によると、デジタルブックは過半数(54.3%)のユーザーに「便利」だと評価されています(不便と感じたのは16.6%)。
特にユーザーから支持されているのは以下の点です。
デジタルブックは、その多機能性から企業において主に3つの目的で活用されています。
商品カタログ、企業パンフレット、大学案内、スーパーのチラシなどをデジタル化します。
デジタルブックにすることで、顧客は資料ダウンロードや資料請求の手間をかけずに、気軽に情報に触れることができます。メルマガにリンクを記載して広く情報を届けたり、動画を資料内に組み込んで視覚的に訴求したりも可能です。カタログやパンフレットの機能を拡張し、商品の魅力を多角的にアピールできるようになります。
製品マニュアルや従業員向けのトレーニング資料としても活用されています。
例えば、新人社員向けのトレーニングマニュアルをデジタルブック化し、各セクションに動画やインタラクティブなクイズを配置することで、楽しみながら学べる環境を提供できます。動画や仕掛けを組み込むことで学習効果を高め、スキル向上や業務理解を早めることが期待できます。また、閲覧環境さえあればどこでもアクセスできるため、業務で迷った際にも素早く資料を参照でき、情報検索にかかる時間を短縮できます。
製品やサービスの利用方法をユーザーに分かりやすく伝える場合に役立ちます。
操作マニュアルやヘルプページをデジタルブックに変換することで、ユーザーは必要な情報に簡単にアクセスし、問題解決やトラブルシューティングをスムーズに行えます。検索機能を組み込めば、UXの向上にもつながります。文章の補足として動画を挿入することで、さらに分かりやすい情報提供が可能です。
デジタルブックの導入を検討する際、「既存のPDFファイルとの違いは何か」という疑問を持たれる方が多いでしょう。ここでは、機能性や閲覧体験における両者の具体的な違いを説明します。
| 項目 | デジタルブック | PDFファイル |
|---|---|---|
| 操作性 | 本やカタログのようにページをめくりながら読める。目的のページに素早く移動しやすい。 | 縦スクロールが基本。ページ数が多いと読み飛ばしや目的のページを見失うことがある。 |
| 表示速度 | ウェブコンテンツとして表示するため、ページ数に関わらずスムーズに閲覧できる。好きな箇所から読み進められる。 | 全てのデータをダウンロードしてから表示するため、データ容量が大きいと表示が遅くなり、「重い」と感じることがある。 |
| 読まれやすさ | ある調査では、PDFに比べて全頁確認されやすく、最後まで読まれやすいという結果が出ている。 | gooリサーチの調査では、ユーザーから敬遠される傾向にあることが判明している。 |
デジタルブックとPDFでは、利用できる機能に大きな違いがあります。
デジタルブックでは、音声や動画を資料内に直接埋め込むことができます。これにより、より詳細で魅力的なリッチコンテンツとして活用が可能です。PDFもURLを貼ることはできますが、埋め込みには別途ツールが必要であり、埋め込むほど表示速度が遅くなる傾向があります。デジタルブックはツールを使わずスムーズに埋め込み可能です。
資料を配信した際、PDFでは「何人がダウンロードしたか」という回数しか把握できませんが、デジタルブックでは「どのページがどれくらい見られたか」という詳細なログデータを取得できます。このデータを解析することで、ユーザーの興味関心に基づいた恒常的な業務改善やマーケティング戦略の立案が可能です。
PDFでは、一度ダウンロードされた資料を遠隔で最新情報に更新したり、記載データを削除したりする管理ができません。一方、デジタルブックでは、元データを修正して差し替えるだけで、閲覧者側のデータも自動的に全て最新の状態に変換されます。これにより、常に正しい情報をユーザーへ提供し続けることができます。
デジタルブックでは、画像の切り取りやメモ・ペイントの書き込みが可能で、それらを他のユーザーとシェアすることもできます。
デジタルブックの導入は、従来の印刷物では実現できなかったデジタルならではの様々なメリットをもたらします。
デジタルブックは紙を使用しないため、従来かかっていた印刷代や製本代などのコストを大幅に削減できます。郵送も不要となるため、郵送代や郵送にかかる工数を削減することも可能です。企業によってはデジタルブックの導入で数百万円規模のコスト削減を実現しています。
デジタルブックは知識不要で誰でも簡単に作成できるのが大きな魅力です。作成したデジタルブックは、URLを共有するか、Webサイトに埋め込むだけですぐに公開できます。
また、印刷物では修正に刷り直しが必要ですが、デジタルブックでは公開後でも新しい資料に差し替えるだけで、共有したURLはそのままで情報が更新されます。例えば、カタログの商品名に誤字が発覚した場合でも、元データを修正して再アップロードすれば、公開済みのデジタルブックが自動で修正後のデータに更新されます。
紙を使用しないため部数の制約がなく、より多くのユーザーに資料を閲覧してもらえます。一度公開してしまえば、閲覧数に制限がなく公開を維持できることに加え、在庫切れや増刷のための追加費用の心配も不要です。少ないコストで多くのユーザーに情報を届けることができます。
電子ファイルによる情報提供では、ユーザーのデバイス環境によって表示ができなかったり、レイアウトが崩れたりする問題が起こりがちです。デジタルブックはどのデバイスからでもブラウザ経由でアクセスできるため、ユーザーの環境に依存せずにコンテンツを提供できます。また、デバイス一つで場所を選ばずに閲覧できるため、営業活動における利便性もメリットの一つです。
デジタルブックの導入は多くの利点をもたらしますが、その特性上、従来の紙媒体やPDFにはない注意すべき点が存在します。ここでは、導入時に考慮し、対策を講じるべきデメリットを解説します。
デジタルブックはWebブラウザを通じて閲覧される形式が一般的です。そのため、紙のカタログやダウンロード済みのPDFとは異なり、インターネットに接続できる環境が必須となります。電波状況が不安定な地下や山間部、あるいはWi-Fi環境がない場所ではスムーズな閲覧が難しくなることがあります。
カタログを閲覧する層に、デジタル機器の操作に不慣れな高齢者やITリテラシーが低いユーザーが多い場合、操作方法で戸惑ってしまう可能性があります。紙をめくる感覚は再現されていても、検索機能や動画再生といったデジタル特有の機能が理解されにくい場合があります。
紙のカタログは自由に広げられますが、デジタルブックは閲覧するデバイスの画面サイズに表示が依存します。特に大きな図面や複雑なグラフをスマートフォンなどの小さな画面で閲覧する場合、縮小表示や拡大操作が必要となり、紙媒体と比較して視認性が低下することがあります。
印刷物では指定された色(特色など)が正確に再現されますが、デジタルブックはユーザーが利用するデバイスのディスプレイに表示されるため、端末や設定によって色の見え方(再現性)に差が出ることがあります。
デジタルブックの作成方法は、主に以下の2つがあります。
デジタルブック作成ツールにはPCにインストールする「PCソフトウェア型」と、ブラウザベースで完結する「SaaS/クラウド型」がありますが、ここでは手軽な「SaaS/クラウド型」をご紹介します。
「SaaS/クラウド型」の最大の特徴は、ブラウザ上で利用できるため、インターネット環境さえあればいつでも誰でもデジタルブックを作成できるという点です。シンプルな機能が多く制作難易度も低いため、難しい知識がなくてもすぐに作成できます。
また、作成ツールでは自分でコンテンツを管理できるため、好きなタイミングで資料の更新ができるなど、自由度が高いというメリットがあります。無料で利用できるツールも登場しているので、「まずは試しに利用してみたい」という方にもおすすめの方法です。
制作代行は、印刷物の原本を業者に渡して、スキャンからデジタルブック化までを代行してもらうサービスです。
「1冊○○円〜」と費用がかかるほか、冊数やページ数によって従量課金が発生するため、1回のみの制作で済むユーザーや、更新頻度が低いユーザー、予算が豊富にあるユーザーなどに向いています。コンテンツの更新や修正のたびに、内容を逐一業者に指示する必要があるため、作成ツールに比べると自由度は下がる点に注意が必要です。

「ActiBook(アクティブック)」は、PDFやWord、Excel、PowerPointなどのファイルを、パソコン・スマートフォン・タブレットで閲覧可能なデジタルブックに変換できるツールです。紙冊子のレイアウトを保ちながら、簡単な操作で電子化でき、マニュアルや手順書の共有方法を効率化します。ページ別の閲覧数や検索キーワードなどを記録し、どの情報がよく参照されているかを把握できる機能もあります。
頻繁に改訂が必要な資料は、印刷や再配布の負担が大きくなりがちです。ActiBookを導入すると、電子化した資料をリンクで共有でき、更新後も同じURLからアクセス可能になります。配布作業の手間を減らしつつ最新情報を届けられます。
また、検索機能付きのデジタルブックとして活用できるため、必要な情報を探しやすくなります。無料プランも用意されており、初期費用をかけずに効果を検証しながら運用範囲を広げられます。
参考:3ステップでデジタルブックの作成から配信まで可能|ActiBook(アクティブック)
デジタルブックは、紙媒体の操作性を保ちながら、動画・音声の組み込み、閲覧ログの取得といったデジタルならではの強力なメリットをもたらします。これにより、コスト削減、情報更新の迅速化、そして営業・マーケティング活動の高度化が実現できます。
まずは、費用や専門知識の心配なく始められる作成ツール、特に無料プランがあるActiBookを活用し、お手元の資料をデジタルブック化して、その操作性や効果をぜひご自身で体感してみてください。



ActiBookは顧客の興味行動が分かり 効率的・効果的なセールス活動を 促進する電子ブック作成ツールです
ダウンロード資料の内容