最終更新日
公開日
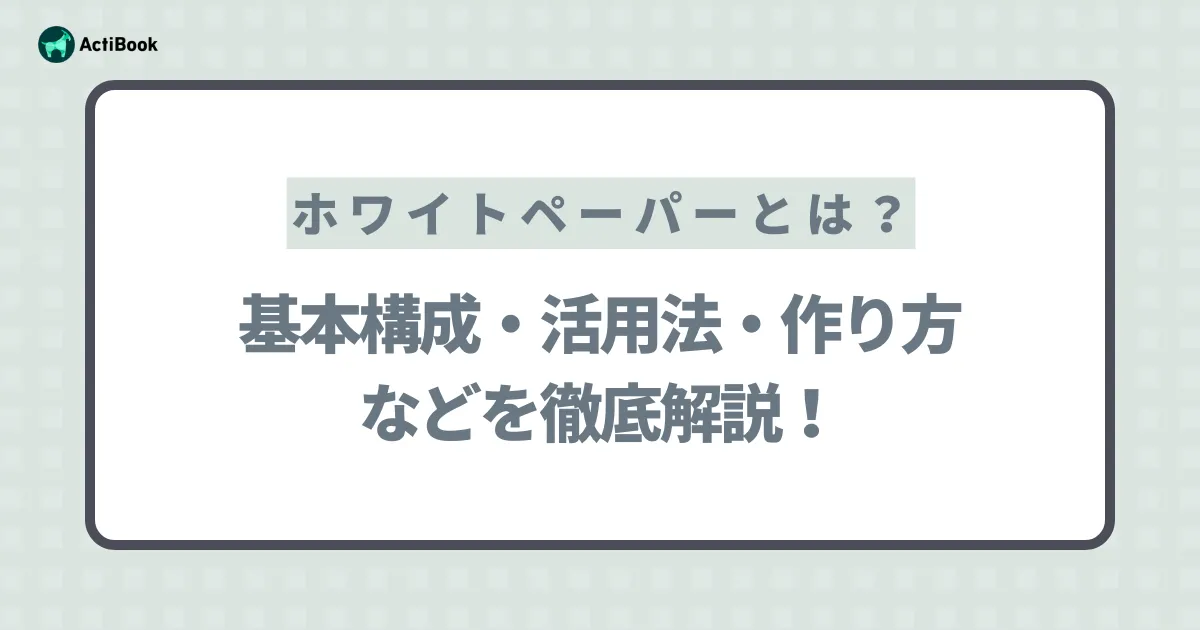
ホワイトペーパーは、特定のテーマに関する専門的な情報や課題解決のヒントをまとめた資料です。
単なる営業資料ではなく、見込み客にとって価値のある情報を提供することで、見込み客との初期接点や信頼構築、リードの育成を目指します。
本記事では、ホワイトペーパーの基本的な構成や活用法から、作成方法、配布方法に至るまで、成功するホワイトペーパー作りのためのポイントを徹底解説します。また、制作の難易度や費用、自社での制作から外部依頼まで、柔軟に対応できる方法を紹介します。
目次

ホワイトペーパーとは、特定のテーマに関する専門的な情報や課題解決のヒントをまとめた資料のことを指します。BtoB領域のマーケティングで広く活用されており、見込み客との初期接点や信頼構築、リードの育成に効果的です。
商品やサービスを直接売り込むのではなく、まずは顧客にとって価値のある情報を提供することで、興味関心を引き出し、将来的な導入検討につなげることができます。顧客の課題に寄り添う情報発信ツールとして、今や欠かせない施策となっており、多くの企業が取り組んでいます。
ホワイトペーパーと営業資料は、目的や作成の視点、活用シーンに明確な違いがあります。
ホワイトペーパーは顧客目線で作成され、主に課題解決やノウハウ提供を目的として提供される資料です。情報収集段階の見込み客に向けて提供するのが基本です
一方、営業資料は企業目線で作られ、自社製品やサービスの特徴・優位性を伝えるための資料です。商談や提案の場で直接的なアプローチに使用されます。
それぞれの特性を理解し、適切なタイミングで使い分けることが重要です。
ホワイトペーパーと白書は混同されがちですが、その役割は異なります。
白書は政府や公的機関が発行する正式な報告書で、政策や社会状況についての現状や課題をまとめた公文書です。
一方、ホワイトペーパーはこの白書の概念をもとに発展したもので、民間企業がマーケティング目的で作成する資料を指します。主に自社の製品・サービスに関連する情報や課題解決策を提供し、見込み顧客との接点や信頼構築に活用されます。
ホワイトペーパーを適切に活用すれば、リード獲得や商談機会の創出、企業ブランディングにもつなげることができます。ここでは、ホワイトペーパーの具体的な活用方法について詳しく解説します。
ホワイトペーパーは、見込み客の創出と育成に効果的です。
ホワイトペーパーのダウンロード時に企業名やメールアドレスなどの情報を入力してもらうことで、潜在的な関心を持つユーザーのデータを収集できます。取得した見込み客には、メルマガ配信やセミナー案内などの継続的な情報提供を行うことで、段階的に関係を構築することが可能です。
こうしたアプローチによって、興味関心を育て、最終的に購入へとつなげられます。
ホワイトペーパーを通して、自社の専門性や独自の知見をアピールできます。業界の最新動向や実践的なノウハウをわかりやすくまとめることで、読者に「この分野ならこの企業」と想起させる印象を与えることが可能です。
信頼性や知識の深さをアピールすることで、企業のブランド価値を高め、長期的なファンや協業先との信頼関係の構築にもつながります。 質の高い情報を発信することが、ブランディング成功のカギとなります。
ホワイトペーパーは、見込み客や既存顧客が抱える疑問や課題を解消し、満足度を高めるために活用されます。たとえば、導入時の不安を払拭するガイドや、便利な使い方を紹介する資料を提供することで、ユーザーに安心感と納得感を与えられます。
また、既存顧客も悩みなどを解消できるため、良好な関係を築くきっかけにもなり、商品やサービスへの理解と愛着を深めることが可能です。顧客視点に立った情報発信を行うことが大切です。
ホワイトペーパーには、自社の強みやサービスの詳細、導入効果などが体系的に整理されているため、営業資料としても有効活用できます。必要に応じて内容を調整すれば、商談時の資料として即戦力になるだけでなく、資料作成にかかる時間や手間も大幅に削減可能です。
また、情報が整理されていることで、社内外の営業担当者が同じ軸で訴求できる点も大きなメリットです。効率的な営業活動を支えるツールとして重宝されます。
ホワイトペーパーは、専門的なノウハウや自社サービスの情報をわかりやすくまとめているため、社内教育用の資料としても有効です。特に業界未経験の新入社員や異動者にとっては、業界動向や商品知識を体系的に学べる教材として役立ちます。
難解な専門用語を避けた構成が多いため、教育現場でも扱いやすく、短期間での理解促進にも貢献します。既存資料と組み合わせて研修を効率化することも可能です。
一口にホワイトペーパーといっても、目的やターゲットに応じてさまざまな種類があります。製品紹介に特化したものから、業界課題の解決策を示すものまで、内容や役割は多岐にわたります。
ここでは、代表的なホワイトペーパーの種類と、それぞれの特徴についてわかりやすく解説します。
課題解決型ホワイトペーパーは、読者の抱える疑問や悩みに対し、自社のノウハウや専門知識を活かして具体的な解決策を提示することを目的としています。初心者向けの入門ガイドから、上級者向けの高度なテクニックまで幅広いテーマに対応でき、ユーザーのニーズに応じた情報提供が可能です。
読者にとって実用的な内容を提供することで信頼感を醸成し、結果的に自社サービスへの関心や導入意欲を高める効果も期待できます。
ワークシート型ホワイトペーパーは、空欄に記入したり数値を入力したりするだけで、すぐに業務へ活用できる実用的な資料です。自社で提供しているサービスの一部機能をテンプレート化して配布することで、「試してみたい」と思わせるきっかけにもなります。
たとえばKPI設定シートやスケジュール管理表など、業務の具体的な支援につながる内容にすることで、ダウンロード率の向上や見込み顧客の育成にも効果的です。
製品・サービスの紹介型ホワイトペーパーは、「〇〇に役立つツール」などのテーマを設定し、複数の製品を比較・紹介する形式です。読者にとって公平な視点を保ちながら、自社のサービスも自然に含めることで、押しつけ感なく魅力を伝えることができます。
特に購入を検討している段階のユーザーにとって、有益な判断材料となりやすく、導入の後押しとなる重要なコンテンツのひとつです。
レポート型ホワイトペーパーは、公的機関や業界団体のデータをもとに、自社の視点で分析・考察を加えた資料です。市場動向や業界の課題を深く掘り下げ、独自の調査やアンケート結果を反映させることで、信頼性とオリジナリティのあるコンテンツを提供できます。
情報収集や分析にコストはかかるものの、読者からの信頼や権威性を得やすく、マーケティング担当者や経営層にとって有益な資料となります。
事例紹介型のホワイトペーパーは、自社サービスを導入した企業の、実際の成功事例をまとめた資料です。導入前に抱えていた課題、導入に至るまでの経緯、導入後に得られた成果、そして今後の展望までを時系列で丁寧に紹介します。
読者にとっては、具体的な活用シーンや効果をイメージしやすく、導入の判断材料になります。実際のユーザーの声を盛り込むことで、信頼性と共感を高められ、商材導入の後押しをすることも可能です。
セミナー資料型は、自社が主催したイベントやウェビナーの内容をまとめたホワイトペーパーです。講演内容の要点や参加者の反応、実際のスライドや当日配布された資料などを盛り込み、臨場感を持って内容を伝えます。
参加できなかった層にも価値ある情報として届けられ、イベントへの興味や次回参加のきっかけにもなります。登壇者の発言や質疑応答のハイライトを補足すると、理解度がさらに高まり、信頼性も向上します。
効果的なホワイトペーパーを作成するためには、基本となる構成を押さえることが大切です。読者に伝わりやすく、最後まで読んでもらうためには、情報を整理し、ストーリー性を持たせる工夫が求められます。
以下では、ホワイトペーパーに欠かせない基本構成と、それぞれの役割についてわかりやすく解説します。
ホワイトペーパーの表紙は、読者の興味を引く最初の接点です。誰に向けた資料なのかを明確にし、「○○担当者必見」「今すぐ使える○選」など、読者対象や内容を端的に伝えるキャッチコピーを添えることで、ダウンロード意欲を高められます。
加えて、発行日や著者名、自社ロゴなどを記載することで信頼感もアップします。中身に興味を持ってもらうための“入り口”として、表紙の設計は非常に重要です。
次のセクション「資料の目的」もしくは「はじめに」では、ホワイトペーパーで解説する内容や、解決できる課題を簡潔にまとめた内容を紹介します。このパートは、読者に「自分に関係のある情報だ」と感じてもらうための重要な入り口です。
長くなりすぎないよう、ポイントを絞って整理することが大切です。目安としては1ページ程度に収め、全体の流れを把握できるようわかりやすくまとめましょう。
目次は、ホワイトペーパー全体の構成を簡潔に示し、読者が内容を把握しやすくする役割を果たします。通常、目次はホワイトペーパーの冒頭に配置され、各セクションや章のタイトルとそのページ番号を記載します。読者は興味のある部分を迅速に見つけることができ、資料全体の流れを理解しやすくなります。
また、目次は資料の全体像を示すため、読者がどのような情報を得られるのかを把握するために重要な要素となります。レイアウトの都合で「資料の目的・はじめに」と同じページに掲載されることもあります。
ホワイトペーパーの「コンテンツ(中身)」部分は、取り上げるテーマに関する詳細な解説が求められます。まず、問題提起をして課題を明らかにし、その原因を深掘りしていきます。そのうえで、「一般的な解決策」と「自社ならではの具体的な解決法」を順番に紹介する流れが基本です。
たとえば、営業部門における情報共有の課題について書く場合、「情報不足」や「非効率なコミュニケーション」といった問題点を挙げます。そして、自社のツールやサービスがどのようにこれらを解決できるのかを具体的に伝え、読者に実践的なヒントを提供します。
「自社商品・サービスの紹介」では、ホワイトペーパーで取り上げたテーマに関連する自社の製品やサービスを紹介します。たとえば、営業部門での情報共有を支援するツールを取り上げた場合、そのツールがどのように営業担当者間の情報共有を効率化し、業務の生産性向上に貢献するかを説明します。
自社サービスの特長や導入後のメリットを明確に伝え、読者がどのような課題を解決できるかを具体的に示すことが重要です。ただし、コンテンツ(中身)よりもボリュームが多くならないよう注意し、テーマとの関連性を意識した簡潔な紹介を心掛けましょう。
「会社概要」セクションでは、ホワイトペーパーを発行した企業の基本情報を提供します。会社名、所在地、電話番号、FAX番号、代表者名、創立年月日、事業内容などを記載するのが一般的です。また、権威性が求められるテーマでは、制作者の顔写真や名前を掲載することもあります。
読者が信頼できる企業であることを伝えるため、正確で簡潔に記載することが重要です。企業の信頼性や専門性を強調し、問い合わせ情報を明示することで、関心を持った読者が次のアクションを起こしやすくなります。
効果的なホワイトペーパーを作成するには、正しい手順を踏むことが重要です。ターゲット設定からテーマ選び、構成作成、執筆、デザインまで、各ステップを丁寧に進めることで、読者に伝わる質の高い資料が完成します。
本章では、初めての方でもわかりやすいように、ホワイトペーパー作成の流れを順番に解説します。
ホワイトペーパーを作成する際は、まず取り上げるテーマと課題を明確に決めることが重要です。自社の製品やサービスで解決できる課題を1つに絞り、その内容に合わせたホワイトペーパーの種類を選びましょう。
テーマを広げすぎると内容がまとまらず、読者に伝わりにくくなります。たとえば営業支援ツールなら、「営業部門の情報共有の改善」など、具体的な課題に焦点を当てます。ターゲットのニーズを意識して構成を考えることが大切です。
ホワイトペーパーを作成する際には、読者にどのような行動を取ってもらいたいかを明確に目標として設定することが重要です。具体的なアクションとしては、ホワイトペーパーのダウンロード後に「さらなる詳細資料のダウンロード」や「無料相談の申し込み」「サービスデモの予約」などの行動を目標として設定することが考えられます。
目標を明確に設定することで、ホワイトペーパーの内容もターゲットの行動を誘導しやすくなり、商談に繋がる可能性が高まります。
ホワイトペーパーを作成する際には、ターゲットとなる読者層を明確に設定し、その人に合わせた資料を作成することが重要です。たとえば、営業支援ツールに関するホワイトペーパーであれば、ターゲットは営業部門の管理者や担当者になり、そのターゲット層を基に、ペルソナを設定します。
ペルソナには、年齢、性別、職種、業界、抱えている悩みや課題を詳細に設定し、具体的な人物像を明らかにする必要があります。ペルソナを絞り込むことで、よりターゲットにマッチした有益な情報を提供でき、読者にとって価値あるホワイトペーパーを作成可能です。
ホワイトペーパーの全体構成を決める際には、読者がスムーズに読み進められるよう、論理的で自然な流れを意識することが重要です。一般的な構成は「課題の説明→課題の分析→課題の解決→自社ソリューションの紹介」となり、読者が段階的に理解を深め、最終的には解決策として自社製品に興味を持つように導きます。
フォントサイズや行間などの表記ルールも統一し、視覚的に読みやすくする工夫も求められます。また、重要なポイントには画像やグラフを活用し、視覚的に補強します。
200 "・掲載する図表や画像の作成
・写真撮影
・キャッチフレーズの作成
・取引先へのインタビュー(事例紹介の場合)
全体構成とルールを決めたら、ホワイトペーパーで使用する素材を集めましょう。ターゲットにとって有益な情報を視覚的に伝えるために、関連する図表やグラフを作成し、データを分かりやすく提示しましょう。また、場合に応じて写真を撮影し、具体的な事例や導入シーンを視覚化することも有効です。
さらに、キャッチフレーズを工夫して、読者の興味を引き、各セクションの内容を引き立てる工夫も求められます。実際の導入事例や成功事例を紹介するために取引先へのインタビューを行い、信頼性のある生の声を盛り込むことも効果的です。
次に、目次に基づいて各セクションの内容を執筆し、ターゲットに向けた解説文を加え、情報をわかりやすく伝えるように内容を執筆します。手順4で決定した全体構成に、手順5で集めた素材を組み合わせるとスムーズに進められます。
また、図表やグラフを適切に配置し、視覚的に理解しやすい構成にします。デザインの統一感を意識し、ページごとの色やフォントを統一して、読者が一貫して読みやすい印象を持つように仕上げることも大切です。ライティングとデザインのバランスを取ることで、効果的なホワイトペーパーが完成します。
ホワイトペーパーを作成した後は、誤字脱字のチェックが不可欠です。細かな間違いが信頼性を損なう原因になり得るため、内容全体を丁寧に確認しましょう。また、文字と画像の配置にも注意が必要です。ページが詰まりすぎていないか、適切な行間や余白が確保されているかを確認し、読者がストレスなく読むことができるように調整します。
画像やグラフは視覚的に情報を伝えるための重要な要素ですが、適切な大きさと配置にすることで、より効果的に情報を伝えられます。全体のバランスを整えることが、完成度の高いホワイトペーパー作成には欠かせません。
ホワイトペーパーを作成する際は、いくつかの重要なポイントを押さえることで、成果の最大化につながります。ターゲットのニーズを理解し、明確な目的に基づいてコンテンツを作成するほか、読みやすさや信頼性を意識した構成やデザインにも注意を払いましょう。
ここでは、ホワイトペーパー作成時に押さえるべきポイントを具体的に解説します。
ホワイトペーパーは、読者にとって分かりやすく、スムーズに読み進められることが大切です。そのため、専門用語の使用はなるべく控え、誰にでも伝わる言葉で説明しましょう。どうしても専門用語を使う必要がある場合は、注釈や簡単な解説を加えることで、理解のハードルを下げられます。
また、自分では気づきにくい専門用語の多用を避けるために、業界外の人にも一度目を通してもらうと安心です。読者の理解を第一に考えた表現が、信頼性の高いホワイトペーパーに繋がります。
ホワイトペーパーを作成する際は、全体の流れを意識した構成が重要です。課題を提示し、それに対する解決策を順を追って説明する「起承転結」の流れを意識しましょう。
また、結論を最初に伝える方法も効果的です。読者が内容に引き込まれるためには、最初に結論を示し、その後に理由や具体例を説明する「PREP法(結論→理由→具体例→再結論)」を採用するのが良いでしょう。結論が後回しになると、読者は途中で疲れて離脱する可能性が高くなります。
ホワイトペーパーでは、文章だけでは理解が難しい情報もあります。そのため、必要に応じて図、画像、グラフなどの視覚的な要素を活用すると効果的です。特に、データや複雑な概念を伝える際には、視覚的な補助があることで読者が情報を簡単に把握でき、理解が深まります。
たとえば、数値データをグラフで示すことで、直感的に比較や傾向を理解でき、説得力が増します。適切なビジュアルを選ぶことで、ホワイトペーパー全体の見やすさと伝わりやすさが向上します。
ホワイトペーパーは、読者の課題解決を目的とした情報提供ツールであり、広告資料ではありません。過度なセールストークや自社製品の押し出しは、読者にとってノイズとなり、内容への理解や共感を妨げます。
大切なのは、まずユーザーの関心や悩みに寄り添い、有益な情報や具体的な解決策を提供すること。その上で、自然な流れで自社のサービスに触れることで、読者に納得感を与える構成を心がけましょう。
ホワイトペーパーを作成する際は、読む人の視点に立ち、読者が本当に知りたい情報から優先的に構成することが重要です。自社が伝えたい内容であっても、読者ニーズが低ければ後回しにする判断も必要です。
最初に求めている情報が載っていれば、読者の関心を引きつけ、最後まで読んでもらえる可能性が高まります。常に「誰のための資料か?」を意識し、読者の課題に寄り添った構成を心がけましょう。
ホワイトペーパーは一度作ったら終わりではなく、定期的な見直しが不可欠です。顧客のニーズや業界の状況は常に変化しており、内容が古いままだと信頼性を損なう恐れがあります。特に統計や調査データを含む場合は、3年以内の最新情報に差し替えるよう意識しましょう。
情報が古いまま放置されていると、誤解を与えたり、企業イメージに悪影響を及ぼす可能性もあります。常に「最新で正確な情報」を届けることを心がけましょう。
ホワイトペーパーを読みやすく、プロフェッショナルな印象に仕上げるには、全体のデザインに統一感を持たせることが重要です。メインカラーを決め、ページごとに色がバラつかないように配慮しましょう。たとえば、重要なポイントは赤文字、表の背景は淡いグレーなど、色使いにもルールを設けると効果的です。
企業のイメージカラーがある場合は、それを取り入れることでブランディングにもつながります。視認性と一貫性を両立させましょう。
ホワイトペーパーを作成した後は、効果的に配布することが重要です。ターゲットにリーチするためには、どのチャネルを利用するかを慎重に選ぶ必要があります。自社のウェブサイトやSNS、メールマーケティングを活用することで、より多くの読者に届けることができます。
ここでは、ホワイトペーパーの配布方法について、代表的なチャネルや効果的な戦略を解説します。
ホワイトペーパーを効果的に届けるには、自社Webサイトやオウンドメディア、SNSでの掲載が有効です。特にWebサイトはSEO対策と相性が良く、検索上位に表示されれば継続的なリード獲得が見込めます。また、SNSではフォロワーが多いと効果を発揮しやすいです。拡散力も期待でき、異なる層へアプローチできる可能性も高まります。
接点を持つほどダウンロード促進につながるため、日頃から継続的にアカウントを運用するようにしましょう。アクセス状況に応じて広告施策も組み合わせ、認知拡大を図るのが効果的です。
ホワイトペーパーの認知拡大には、プレスリリースサイトや外部メディアへの掲載も有効な手段です。ユーザー数が多い媒体に情報を載せることで、自社サイトやSNSに訪れていない層にもアプローチできます。多様な読者に届けば、より多くのリード獲得にもつながるでしょう。
特に注目度の高い内容であれば、露出を増やすことで一気に関心を集めることが可能です。限られたリソースでも、効率的に配布できる方法としておすすめです。
ホワイトペーパーは、営業資料として商談先に持参することで大きな効果を発揮します。課題の解決策や自社サービスの特長が簡潔にまとめられており、相手にわかりやすく伝える手助けになります。商談先の業種やニーズに応じて、内容をカスタマイズすれば説得力もさらに高まります。
また、資料作成の手間を削減しつつ、自社の専門性を示すツールとしても活用可能です。信頼感を高める営業支援ツールとして、積極的に活用しましょう。
メールマガジンは、ホワイトペーパーを効率よく配布できる手段のひとつです。「○○についてはこちらの資料で詳しく説明しています」といった文言を添えることで、読者の興味を引き、自然な形で資料のダウンロードを促せます。
また、MA(マーケティングオートメーション)ツールを活用すれば、メールの開封率やクリック率を測定でき、リードの関心度を可視化できます。顧客の関心に応じたアプローチが可能になり、商談化への導線としても有効です。
セミナーや展示会、交流会などのイベントでホワイトペーパーを配布することで、見込み客と直接接触できる貴重な機会を得られます。イベントの受付で名刺交換や情報記入をしてもらうことで、参加者の情報を収集し、今後のアプローチに活用できます。
また、ホワイトペーパーを通じて自社の提供する価値や解決策を伝えることで、参加者の関心を引き、自社に対する理解を深めてもらうことができます。資料には連絡先やSNSアカウントを記載し、後の問い合わせやフォローを促進しましょう。
ホワイトペーパーを自社で作成するのが難しい場合、外部の専門家や企業に依頼する方法があります。専門的な知識や経験を持つライターやマーケティングエージェンシーを活用することで、質の高いコンテンツを効率的に作成できます。
ここでは、外部に依頼する際のポイントや、依頼先の選び方について解説します。
ホワイトペーパーを自社で作成するのが難しい場合、ネット上で提供されているテンプレートを活用するのが効果的です。企業が公開している無料テンプレートや、デザインソフトウェアが提供するものなど、さまざまな選択肢があります。
テンプレートでは、空欄を埋めるだけで本格的なホワイトペーパーを作成できるため、デザインや構成に悩むことなく、効率的に制作が進みます。プロフェッショナルな仕上がりが保証されるため、手軽に質の高いコンテンツを提供できるのが魅力です。
ホワイトペーパーの作成が難しい場合、外部の制作会社やフリーランスに依頼するのも一つの方法です。依頼費はかかりますが、専門の知識と経験を持つプロフェッショナルが本格的で読みやすいホワイトペーパーを作成してくれます。
さらに、制作会社によっては、ホワイトペーパーの作成だけでなく、その後のマーケティング施策に関するアドバイスを提供してくれることもあります。外部のサポートを受けることで、ホワイトペーパーを効果的に活用し、より多くのリードを獲得することができるでしょう。
ホワイトペーパーの制作費用は、内容の複雑さや制作に関わる人数、外部に依頼するか自社で作成するかによって異なります。一般的に、専門的なリサーチやデザインが必要な場合は費用が高くなります。
以下では、ホワイトペーパー制作にかかる費用の目安を、さまざまなケースに応じてご紹介します。
ホワイトペーパーを自社で制作する場合、内容やデザインに応じて費用を抑えることが可能です。無料のテンプレートを使用したり、PowerPointに備わっているデザインを活用したりすることで、無料で制作することもできます。
ただし、よりプロフェッショナルなデザインを求める場合、有料のデザインソフトウェアやテンプレートを利用することも選択肢に入ります。
たとえば、デザインソフト「Canva」の有料プランでは、年間11,800円~の会費がかかります(2025年4月11日時点)。有料プランを活用することで、より洗練されたホワイトペーパーを作成することが可能です。
フリーランスにホワイトペーパーの制作を依頼する場合、費用はページ数、デザイン、専門性、リサーチの有無によって大きく変動します。
一般的に、10〜15ページのホワイトペーパーを依頼する場合、費用は10万〜25万円程度が目安です。フリーランスの場合、制作会社と比べてコストを抑えられるのが大きな利点です。
原稿やテンプレートを準備しておくと、スムーズに進行し、コストも節約できます。依頼前にはフリーランスの実績を確認し、イメージに合ったデザイナーを選ぶことが重要です。
外部の制作会社にホワイトペーパーの制作を依頼する場合、費用はページ数やデザイン、専門性、リサーチの有無によって異なります。一般的に、10〜15ページのホワイトペーパーを依頼する場合、費用は15万〜30万円程度が目安です。
制作会社に依頼すると、プロフェッショナルなデザインとライティングが提供され、納期も2週間〜1ヶ月程度が一般的といえます。マーケティング支援を受けたい場合は、制作と共にカスタマージャーニーの設計や戦略的なアドバイスを行う会社を選ぶと効果的です。
本記事では、ホワイトペーパーの基本的な構成や活用法から、作成方法、配布方法などを網羅的に解説しました。
価値の高いホワイトペーパーを作成するためには、ターゲットに合ったテーマ設定やコンテンツ作成、デザインの工夫が重要です。一度作成してしまえば、見込み客の創出や育成、企業イメージの形成、営業資料の効率化など、さまざまな目的で活用できます。適切な配布方法を選べれば、成果の最大化にもつながります。
自社で制作が難しい場合は、テンプレートを活用したり、外部の専門家に依頼するのがおすすめです。質の高いホワイトペーパーを作り、ビジネス成果に繋げましょう。



ActiBookは顧客の興味行動が分かり 効率的・効果的なセールス活動を 促進する電子ブック作成ツールです
ダウンロード資料の内容